教員紹介
-
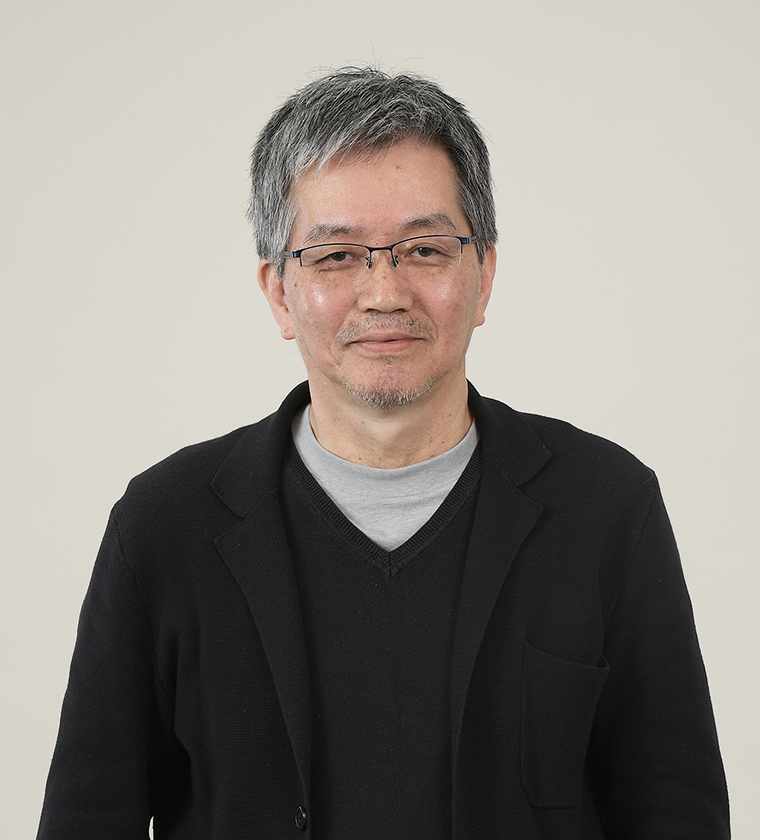
-
古瀬 登 教授NOBORU FURUSE
- 研究テーマ・ゼミ指導分野
- アニメーション
- プロフィール
-
アニメーター、監督、演出、キャラクターデザイン、作画監督。
- 関連リンク・実績
-
『うる星やつら』
『ルパン三世』
『頭文字D』
『ブラック・ジャック』
『エースをねらえ!2』 他
東京メディア芸術学部
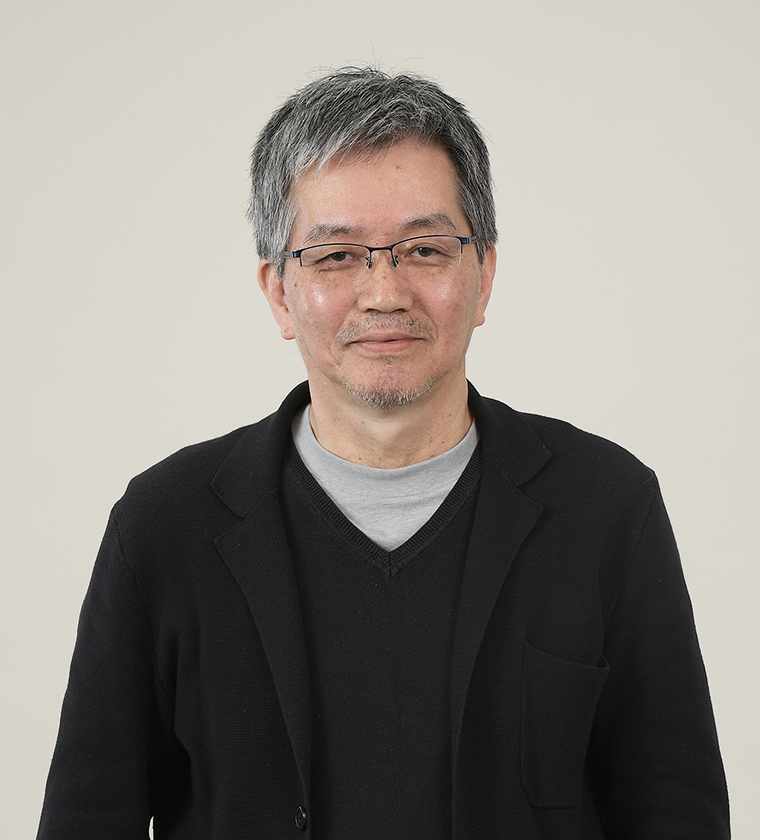
アニメーター、監督、演出、キャラクターデザイン、作画監督。
『うる星やつら』
『ルパン三世』
『頭文字D』
『ブラック・ジャック』
『エースをねらえ!2』 他