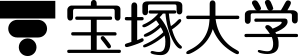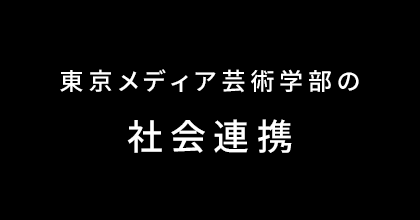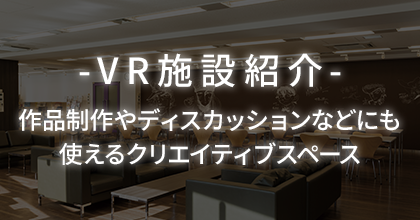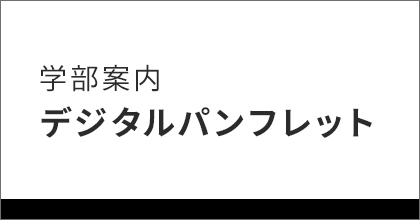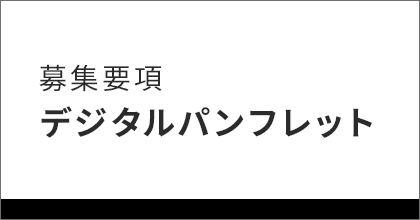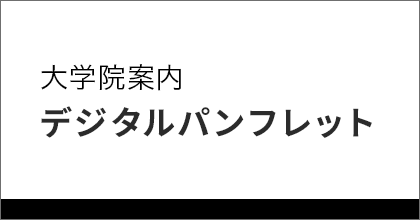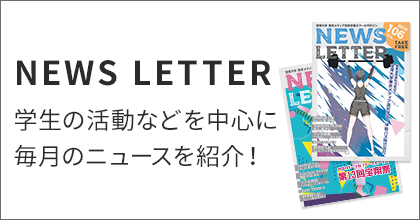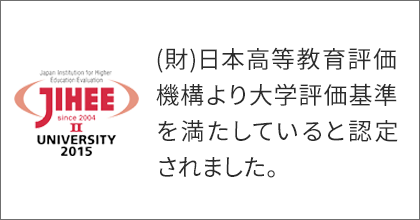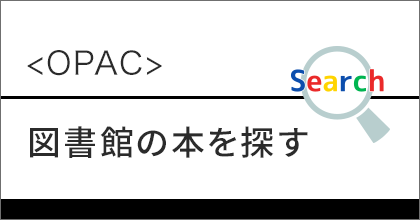メディアデザイン分野

成立させる表現力を磨く
今、世の中ではどういったものが必要とされているのか。それを、広い視点から総合的にリサーチ・分析して、発見した内容を多くの人が理解できるカタチに表現する力を育んでいきます。
企業や地域と連携した演習が多いのも、メディアデザイン分野の特徴です。提示されたコンセプトをデザインに落とし込み、伝える、発表する。進化するメディアをつなぎあわせ、新しいコンテンツを生み出す力を身につけましょう。
4年間の流れ
-
- 1年次
分野を横断して
学ぶ -
各分野を横断して学び、それぞれのコンテンツの魅力と可能性を探りながら、基本的なPCスキルを身につけていきます。
- 【専門科目】
- ● モーショングラフィックスⅠ・Ⅱ
- ● 映像・演出Ⅰ・Ⅱ
- ● ロックミュージック概論Ⅰ・Ⅱ
- ● 色彩構成
- ● デザイン概論Ⅰ・Ⅱ
- ● 造形表現演習Ⅰ
- ● 写真史
- ● 放送概論
- ● 視覚表現Ⅰ
- ● デッサンⅠ
- 1年次
-
- 2年次
デザインの基礎
トレーニング -
デザインの概念を理解し、幅広いメディア表現を体験します。関連するソフトウェアの基本的な技術を習得し、主にグラフィックデザインや空間デザイン、映像や写真の制作を行います。
- 【専門科目】
- ● メディアCG表現Ⅰ・Ⅱ
- ● グラフィックデザイン演習Ⅰ
- ● 映像制作Ⅰ・Ⅱ
- ● 編集デザイン表現Ⅰ
- ● デザイン基礎演習
- ● 撮影技術Ⅰ・Ⅱ
- ● メディアプログラミングⅠ・Ⅱ
- ● 展示論
- ● 映像表現論
- ● 視覚伝達論
- ● コンピュータデザイン演習
- ● 広告表現概論
- ● デザイン企画論
- ● 空間演出演習
- ● Webデザイン論
- 2年次
-
- 3年次
実践を通じて
スキルアップ -
データ分析やリサーチをもとにした企画力を身につけます。一連のデザインプロセスを体験し、実践的なスキルを磨きます。
- 【専門科目】
- ● デザインサーベイ
- ● アドバタイジング演習
- ● インフォメーションデザイン
- ● コンテンツデザイン演習
- ● グラフィックデザイン演習Ⅱ
- ● 編集デザイン表現Ⅱ
- ● タイポグラフィ
- 3年次
-
- 4年次
卒業研究 -
各自が将来進もうとしているジャンルを念頭に、グラフィックデザインや空間デザイン、映像や写真等の自由な観点から卒業研究に取り組みます。
- 【専門科目】
- ● 卒業研究Ⅰ
- ● 卒業研究Ⅱ
- 4年次
学びのPOINT
-

あらゆるメディアを組み合わせて表現 表現を伝えるメディアは日々進化しています。ひとつのメディアでは表現できないこともたくさんあります。本分野では、マンガやイラストレーションから映像、音楽まで、あらゆるメディアを学び、それらを組み合わせて創作していきます。
-

企業や地域と連携した実践的な学びができる 企業や地域の依頼を受けて行う制作や、高校生と協同して取り組むプロジェクトなどは、新たな気づきや成長を与えてくれます。他者とのやり取りや発表を繰り返すことで、どのような道に進みたいのか徐々に明確にしていきます。
-

指導陣は、経験豊富な現役クリエイター 広告業界やメディア業界で活躍するには、「今」を知ることが大切です。宝塚大学の教員陣には第一線で活躍する現役クリエイターが多数在籍。リアルな現場の話が聞けたり、進路の相談にも心強いサポーターとなってくれます。
こんな将来につながる
授業Pick UP!
-


-
撮影技術Ⅱ
デジタル技術の興隆によってメモを取るように撮影を行い、ソーシャルメディアなどを通して共有することが日常化しています。それに伴って、写真や映像に関連する知識や技能が求められています。この授業では、撮影技術Ⅰで習得した基礎的な技術を踏まえ、ライティングを使用した撮影技術の習得を目指します。また、表現者として応用的な撮影や作品制作を行います。
デザインサーベイ
ユーザーのニーズを満たすデザインを行うためには、調査、評価等の統計データを適切に分析しデザインプロセスに取り入れる必要があります。データ分析に基づいたビジュアルデザインを演習形式で学んだうえで、外部から提供された統計データをベースに課題解決に向けたデザイン企画を行います。