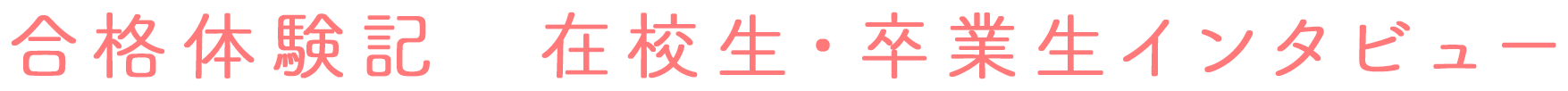
 ">
">
合格者インタビュー 2021
-
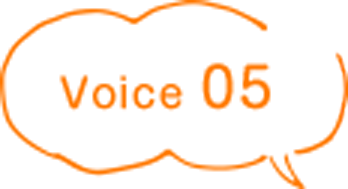

-
看護学部の頃よりも厳しいことや難しいことは多いと思いますが、何故自分が助産師になりたいと思い助産師を志したかを忘れなければ、乗り越えられると思います。周りの仲間や先生に頼って下さい。私たちも支え合いながら乗り越えてきました。
\Profile/ 柴田 唯衣 Shibata Yui
- 学部・学科
- 助産学専攻科
- 出身校
- 宝塚大学
- なぜ助産師の道に進もうと思いましたか?また、宝塚大学助産学専攻科を選んだ理由は何ですか?
- もともと母性領域に興味はありましたが、本格的に志したきっかけは看護学部での母性領域別実習の際、退院後の生活に強く不安を抱えている方と出会いました。そんな方を支えられる医療者になりたいと思うようになりました。地域で妊産褥婦を支えることができ、母性領域のスペシャリストである助産師を志しました。
- 宝塚大学 助産学専攻科に入学して「良かった」思うこと、また「苦しかった・辛かった・大変だった」と思うことは何ですか?
- 良かったことは、コロナ禍で授業が上手く進まず、卒業できるのかと不安を抱えていた際に、先生方が「卒業できるから安心して」と言って下さいました。その言葉が心強かったことを覚えています。学生に寄り添ってくださるような優しい先生方が側にいて下さるのも本学の魅力だと思います。このコロナ禍で授業や課題、就職活動、実習と多くのことを並行して行うことが辛く感じたこともありました。しかし、専攻科の学生みんな同じ状況でしたので、みんなで励まし合いながら頑張ることができました。
- 宝塚大学の特色である「アートとグリーフケア」「アタッチメント・ヨガ」「ベビーマッサージ」の授業はいかがでしたか?また、実習で役立ったこと、今後活かしたいものはありますか?
- 今年はコロナの影響で、ベビーマッサージやアタッチメント・ヨガなどは開催が遅くなったり、毎年行なっていた、ベビーがいるご家庭の方を実際に招いてのベビーマッサージを実施することが難しくなってしまったりと、例年とは異なる形での講義でした。来場型のイベントができなかったので、学生同士で自分たちが考えたマッサージ教室を行い、お互いを評価し合いながら実施しました。ベビーマッサージはマッサージの効果が重要ではなく、親子のコミュニケーションとして実施することが大切であるということを今後、ベビーマッサージインストラクターをしていく上で伝えていきたいと思います。
- 学校や仕事などとの両立はどのように工夫されましたか? (勉強との両立)
- 専攻科の過去問題を見て、国家試験レベルの問題ばかりだったので、国家試験の過去問題を何度も何度も繰り返していました。
- 一番好きな授業は何ですか?また、その理由を教えてください。
- コロナの影響でオンライン授業が多く、入学後すぐに緊急事態宣言が発せられ、授業開始が延期となりました。緊急事態宣言明けに実技の授業が始まりお産の介助練習を行った際、助産師の勉強をしているなと実感しました。今年は新卒者が多く、お産を見たことがない学生が多かったため、みんなでより良い介助方法は何かなどと、試行錯誤しながら練習したことが思い出です。また、今年度は両親学級がオンラインでの配信となり、パソコンで配信動画を制作したり、どのようにすればわかりやすく伝わるかなどを考えながら編集したことも思い出に残っています。
- 実習はどのようなスケジュールでしたか?
- 7月半ばから8週間1つの病院で、お産介助や産科病棟の仕組み、妊娠期から産褥期まで受け持ち、継続事例を受け持つ実習をしました。その後別の病院でお産介助をしました。また、助産所実習や保健福祉センター、助産師会にも行き、地域での助産師の役割についても学びました。
- 実習で特に印象に残っていることはありますか?また、苦労したことはありますか?
- 9月中頃までに9例のお産介助をさせていただくことができ、とても過密スケジュールでした。今年は実習をすることが難しい状況下でしたが、私は病院で、実際の対象者さんを相手に実習させていただくことができました。過密スケジュールの中で自分の体調を整えつつ、実習を実施していくことが難しかったですが、仲間や先生のサポートがあり、乗り越えることができました。
- 1年の専攻科を終えて「助産師」への意識に何か変化はありましたか?
- 助産師像は大きくは変化していませんが、助産師が活躍する場は、周産期現場だけではなく、女性や家族、地域にまで目を向けられる職業なのだと改めて感じました。幅広い知識が必要な助産師だからこそ、その助産師が持つ助産観も重要になるのだと学びました。
- 将来どのような助産師になりたいですか?
- 女性の一生を一緒に考えられる助産師を志したいと考えるようになりました。周産期のみならず、女性の一生に目を向けることで、提供していくケアが変わるのだと学びました。「今」だけではなく、「未来」にも目を向けられる助産師でありたいと考えるようになりました。










