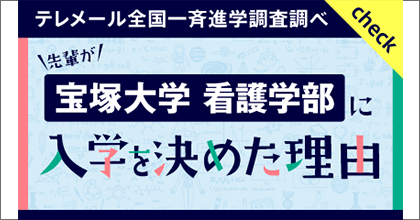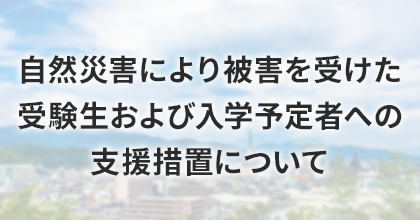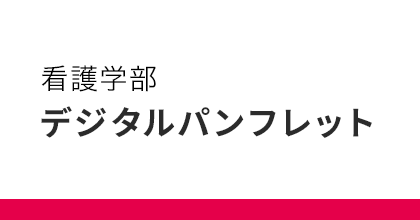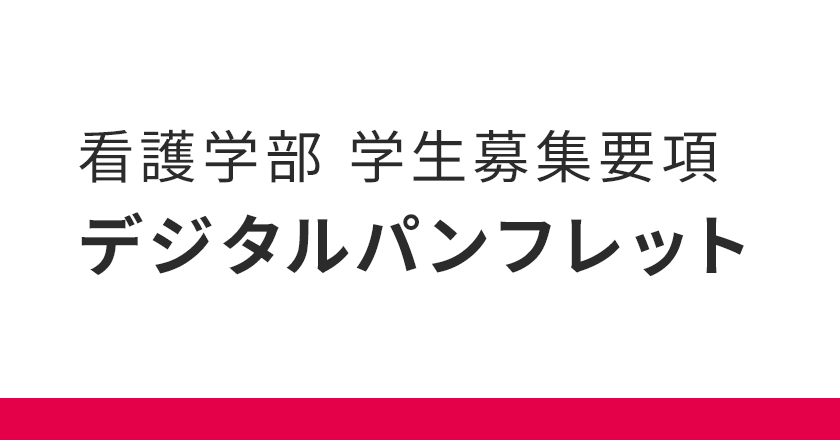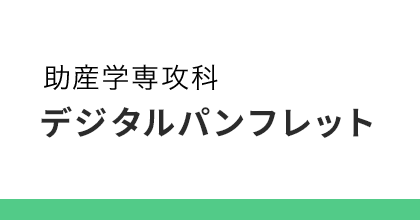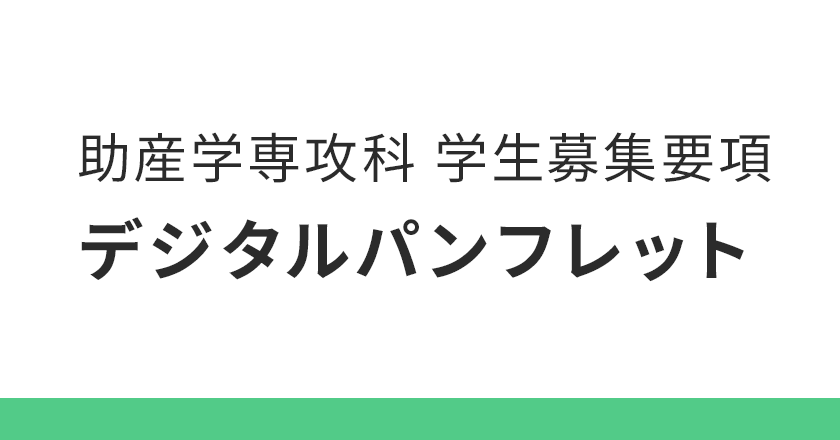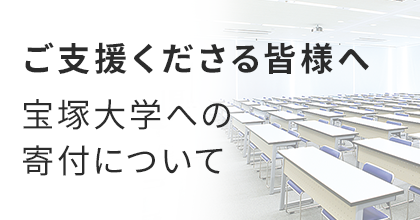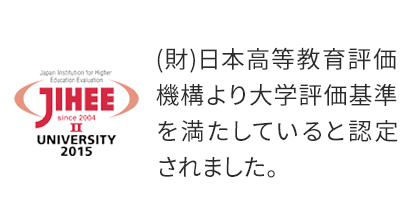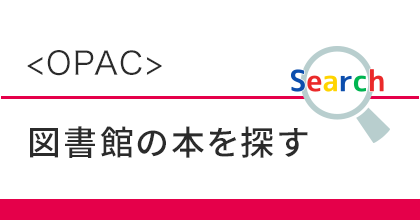看護学部
実習をうけて
看護とアート実習(3年次後期)
対象者の癒しの空間や事故防止のためにアートの知識を活用する看護。
また対象者や家族に与える影響を理解し、環境のなかのアートと看護における創造性に基づくアートについて考察することができる
能力を養うことを実習の目的としている。
看護とアート実習をうけて -レポート-
アートが対象者に与える影響について -すべてのものがアートになる-

私は、看護とアート実習においてさまざまな施設に行き講義などを受けたことで、多くの学びを得ることができた。
また、その学びが今後の実習などにおいて役立つものであると感じた。
そのため本レポートでは、アートが対象者に与える影響と、看護とアート実習における自己の学びについての自己の考えについて述べていく。
5日間の実習は、自分にとって新たな視点をたくさん手に入れることができた。実習の中で取り扱ったものは、ユニバーサルデザインやホスピタルアート、国際的なつながり、病院ボランティアなどさまざまな分野であった。しかし、一つずつを見ると看護には関連がないように見えても、講義や体験を通してすべてのものが看護に関連のあるものであると感じた。
まず、ユニバーサルデザインでは、体に障害を持っている人だけでなく、小さな子どもから高齢者まで幅広い人々が平等に生きやすい世の中にするためにはとても重要な視点が含まれている。そのうえで看護を行う中でも、疾患などによる障害はあるがそれを抱えたうえで、対象者が生活しやすいように援助を考えるという視点を持つためにはユニバーサルデザインの考え方が大きく影響を与えると感じた。
次にホスピタルアートでは、病院の中にアートを取り入れることで無機質な場所から、温かみのある場所に変わるということを体感した。そのため、病院の中でアートを取り入れることは、対象者にとって寂しい場所から安心できる場所に変わると考える。そして、病院に温かい雰囲気があることによって医療者の雰囲気も柔らかくなり、病院に来ていた人々の表情も明るいように感じた。
JICAでの実習は、SDGsや国際協力などの普段自分から進んで聞かない話を聞き、日本の問題だけでなく世界で起こっている問題も日本にとって関係のあることだという視点が増えた。また、海外で言語や文化の違いがある中でも、関係性を築くことができたという話を聞き、看護を行う上で対象者がどんな人であったとしても、まずは相手の思いを受け止めることが重要であると感じた。
最後に病院ボランティアの活動についての話を聞いて、誰かのために何かをしたいと思うことは大きな活動力につながるということを感じた。
ボランティア活動は、自身の時間を使ったうえで、病院に来る人や入院している人ができるだけ明るい気持ちになれるようにアイデアを出し合って計画し、無償で実施しているということを聞いて、何かをしようとする思いはたくさんの人を巻き込んで、一体感を生み出すことにつながっていると考えた。
これらのことから、アートは対象者の不安や恐怖を取り除く物の1つとして大きな役割があると考える。また、人と人とのかかわりもアートであると考える。なぜなら、アートに決まった形はなく、人によって捉え方も異なることから、正解がないと考えるからである。だから、コミュニケーションにおいて相手のことを考え、自分の思いを伝えようとして関係性を構築することはアートであると思う。
そのため、医療者と対象者という関係だけでなく、人と人とのかかわりにおいて相手のことを尊重し、お互いが寄り添っていくことが必要であり、そのために物理的なアートがきっかけとなって、よりよい関係やよりよいものを作り出すことができ、その過程にあるすべてのものがアートになると考える。
看護学部看護学科 柳瀬 紅葉